10月。
ぼくにとっては、5月と並んで特筆すべき存在であるこの月は、日本人の持つ豊かな季節感の中でも一層、明るく切なく、そして哀しく美しい特別な月です。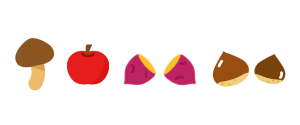 穏やかに色付いていく蜜柑色の陽射しが照らし出す街に、明るい哀しみが幾重にも降り積もります。それぞれに宿した影が日毎に淡く滲(にじ)んでいくのと引き換えに、ひんやりと冷たい風の中、人も町もくっきりとその輪郭(りんかく)を取り戻していきます。
穏やかに色付いていく蜜柑色の陽射しが照らし出す街に、明るい哀しみが幾重にも降り積もります。それぞれに宿した影が日毎に淡く滲(にじ)んでいくのと引き換えに、ひんやりと冷たい風の中、人も町もくっきりとその輪郭(りんかく)を取り戻していきます。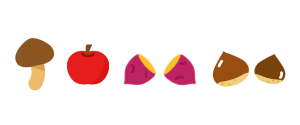 やがて金木犀の香りが届くと、心も身体も秋の深まりを感じ始めます。昔から、なぜかこの金木犀の香りが好きだったぼくです。
やがて金木犀の香りが届くと、心も身体も秋の深まりを感じ始めます。昔から、なぜかこの金木犀の香りが好きだったぼくです。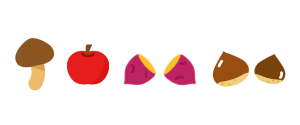 数年前の秋(11月の初めだったと思います)、突然のように京都・東山の紅葉が観たくなったぼくは、休みの前日、一日の仕事を終えたその足で最終の大垣行きに飛び乗って京都を訪れたことがありました。東京近郊の山がかった場所では紅葉もすっかり盛りを過ぎていたため、何の疑いもなく京都を目指したのです。ところが夜行列車はぼくがうとうととまどろむうちに紅葉前線を追い越してしまったらしく、目的の東山では気の早い楓の木が、まるで頬を染める少女のようにわずかに色付いているだけで、期待していた全山紅葉の景色には程遠い有様だったのです。
数年前の秋(11月の初めだったと思います)、突然のように京都・東山の紅葉が観たくなったぼくは、休みの前日、一日の仕事を終えたその足で最終の大垣行きに飛び乗って京都を訪れたことがありました。東京近郊の山がかった場所では紅葉もすっかり盛りを過ぎていたため、何の疑いもなく京都を目指したのです。ところが夜行列車はぼくがうとうととまどろむうちに紅葉前線を追い越してしまったらしく、目的の東山では気の早い楓の木が、まるで頬を染める少女のようにわずかに色付いているだけで、期待していた全山紅葉の景色には程遠い有様だったのです。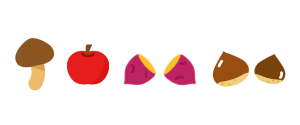 ところが、すっかり気落ちして山を下り、祗園(ぎおん)辺りの町並みに足を踏み入れた瞬間でした。金木犀の香り・香り・香り…。普段はしっとりと鼻先をかすめ、はっと気付いたぼくが改めて深呼吸をしてみても最早それともわからないほど微かな橙色の甘い花の香りが、そこ祗園界隈(かいわい)では庭先といわず街路といわず、そう、町を包んだ空気そのものを鮮やかに染め抜いていたのです。町にそれだけの金木犀が植えられているということ。そしてその金木犀が今まさに満開のときを迎えようとしていること。紅葉には一足早かったけれど、期せずして満開の金木犀に間に合ったぼくは、何だかとても得をした気持ちになったことを覚えています。
ところが、すっかり気落ちして山を下り、祗園(ぎおん)辺りの町並みに足を踏み入れた瞬間でした。金木犀の香り・香り・香り…。普段はしっとりと鼻先をかすめ、はっと気付いたぼくが改めて深呼吸をしてみても最早それともわからないほど微かな橙色の甘い花の香りが、そこ祗園界隈(かいわい)では庭先といわず街路といわず、そう、町を包んだ空気そのものを鮮やかに染め抜いていたのです。町にそれだけの金木犀が植えられているということ。そしてその金木犀が今まさに満開のときを迎えようとしていること。紅葉には一足早かったけれど、期せずして満開の金木犀に間に合ったぼくは、何だかとても得をした気持ちになったことを覚えています。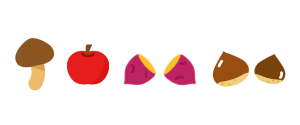 10月、神無月。
10月、神無月。
「鬼の居ぬ間に洗濯」という諺(ことわざ)がありましたが、さて、神様のいない間に、一体ぼくらは何をしておけばいいのでしょうね。
文責:石井





