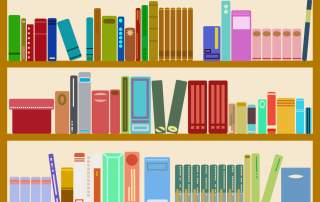【アーカイブ69】旅の便り
星明かりにほうっと白く浮かび上がるしっとりと露を含んだ砂浜に腰を下ろして、天の川から這い出た格好の巨大な<さそり座>を仰ぎ見る。 羽田から那覇へと向かう飛行機の窓から見た、蒼空に夢のようにかかった真昼の上弦の月が、およそ12時間かけて空を巡り、今ゆっくりと西の果てに沈んでいく。すると待ち構えたように夜空の星たちがより一層輝きだす。北緯26度線に近い慶良間諸島のここ渡嘉敷では、<さそり座>も10度ばかり高度を上げて東京で見るのとは比べものにならない存在感を示している。アンタレスの赤い炎がちろちろと夜空を焦がすのも怪しい。久しぶりに見る天の川の対岸には、きりっと引き絞った大弓を今にも射掛けようとする緊張感で、南斗六星の<射手座>が<さそり座>に睨(にら)みをきかせている。 南の水平線から煙るように立ちのぼる天の川を天頂方向へたどると、天の川を隔てて<こと座>のベガと<わし座>のアルタイル、そして磨き上げられたばかりの神々しさで南へと羽ばたいていく<白鳥座>のデネブ。めまいがするほどの星くずのせいか、いつもは難なく視認できる<夏の大三角>がかろうじてそれとわかる程度だ。昨夜は古式に則った「七夕」の夜で、天の川に架かった「鵲の渡せる橋」を通じて牽牛と織女の一年一度の逢瀬が遠く望めたのだった。 それから北の空に<こぐま座>の北極星を探してぼくは一瞬戸惑う。見慣れた場所にその姿はなく、山際に沈みかけた心配げな母熊の姿を便りにその所在を突き止めると、東京と僅か10度差とはいえ驚くほど低い空にそれはかかっていた。それでも北極星を確認すると何とはなしに人心地がついて、それからぼくは改めて北東の空に上り始めた<カシオペア座>のWと、その東に隣接する<アンドロメダ座>を確認する。時と共にやがて北東の山陰からペルセウスがその勇姿を現すだろう。今日は<ペルセウス座流星群>の活動が極大となる夜だ。そうしてぼくは、久しぶりに天の川に沿った夏の星巡りの旅を存分に楽しんだ。 一人で眺めるにはあまりにももったいない、気の遠くなるような星空の下で、やがてぼくは寝転がって、そばにいて欲しかった仲間たちのことを想い始める……。 慶良間諸島の玄関口である渡嘉敷島へは、那覇の泊港から高速艇でわずか35分。うとうととほんの少しまどろむと、いつの間にか海はまるでグラデーションのように藍から鮮やかな青へと変化している。港まで迎えに来た民宿のワゴン車で阿波連ビーチを目指し峠を登り詰めると、慶良間の島々に囲まれた切ないほどに美しい珊瑚礁の海が眼下に広がる。 白い砂浜、光の加減で色を変えるケラマブルーの海、点在する緑の島影、垂直に近い仰角87度の陽射しに目を細めて眺める水平線、珊瑚礁の海を群れ飛ぶ色とりどりの熱帯魚。それは、いつでもぼくが思い焦がれ続ける夏の風景だ。 ぼくは自分でも信じられないような、鳥肌が立つ程の緊張感と高揚感とを持て余しつつ、波間へと泳ぎ出す。細胞のひとつひとつに記憶された太初の海が、この慶良間の海と感応し合い波立っている。息を詰めて海中に身を没すると、数え切れない熱帯魚たちの好奇に満ちた視線に射抜かれる。そうしてぼくは次第に透き通っていく心を感じながら、いつまでもいつまでも波に身を任せていた。 白い砂浜に立って強過ぎる陽射しに目を細め沖の島々を遠く眺める瞬間にも、珊瑚礁を群れ飛ぶ色とりどりの熱帯魚と戯れる瞬間にも、落ちていく夏の太陽がスミレ色に染める海の美しさに目を見張る瞬間にも、そして気の遠くなるような星空の下、今この瞬間にも、肩を並べて同じ時間を呼吸する仲間たちの存在を求めているぼくがいる。繰り返し一人で、こうして沖縄を訪れるのは、まるでそのことを確認するためでもあるかのようだ。 突然の歓声に我に返る。三々五々浜に下りて星見を楽しむ人々の目が空の一点に注がれる。時折思い出したように流星が空を駆ける。気が付けば北東の空には<ペルセウス座>が低く架かり、メドゥーサの額にアルゴルが怪しく輝いている。 光の帯が長く尾を引いて夜空を切り裂くと、今にも満天の星を散りばめた夜の帳(とばり)が二つに裂けて、そこから天の啓示のように地上を照らす陽光が現われそうな錯覚を一人楽しむ。 どれ程の時間をそうして過ごしただろう。 やがて少し風が出て、星明かりにぼんやりと見える波打ち際で、海がざわめき出した。 明日はいよいよ本島へ帰る日となった。 ぼくはゆっくり立ち上がると腰の砂を払った。来年のことはわからないけれど、何としても再びこの海に帰ってこようと、ぼくは一人決心をして、少し雲が出てきた空をもう一度仰ぎ、砂浜を後にした。 ......